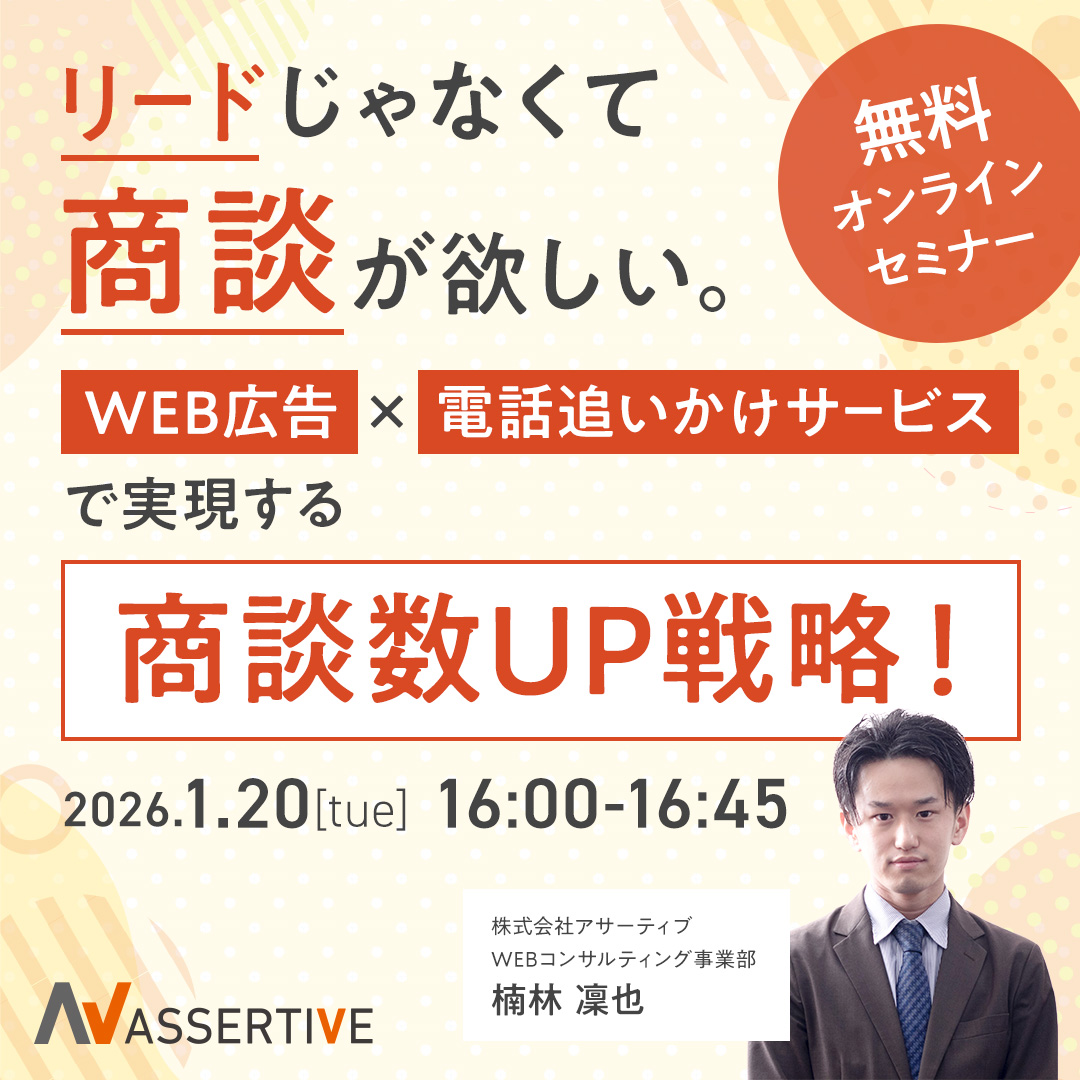Webマーケティングを強化するには、まず「自社が今どんな立ち位置にいるのか」を正しく把握することが大切です。その第一歩となるのが競合分析です。
競合分析では、客観的なデータをもとに他社の戦略や成果を読み解くことで、自社の強みや弱み、次に注力すべきポイントが見えてきます。何から着手すべきか迷っている方にとっても、優先順位を整理する上で非常に有効です。
本記事では、競合分析の重要性から見るべき指標の選び方、実際の調査手順までをわかりやすく解説しています。Webマーケティングにおける競合分析を進める際のガイドとして、ぜひご活用ください。
Webマーケティングにおける競合分析の意義
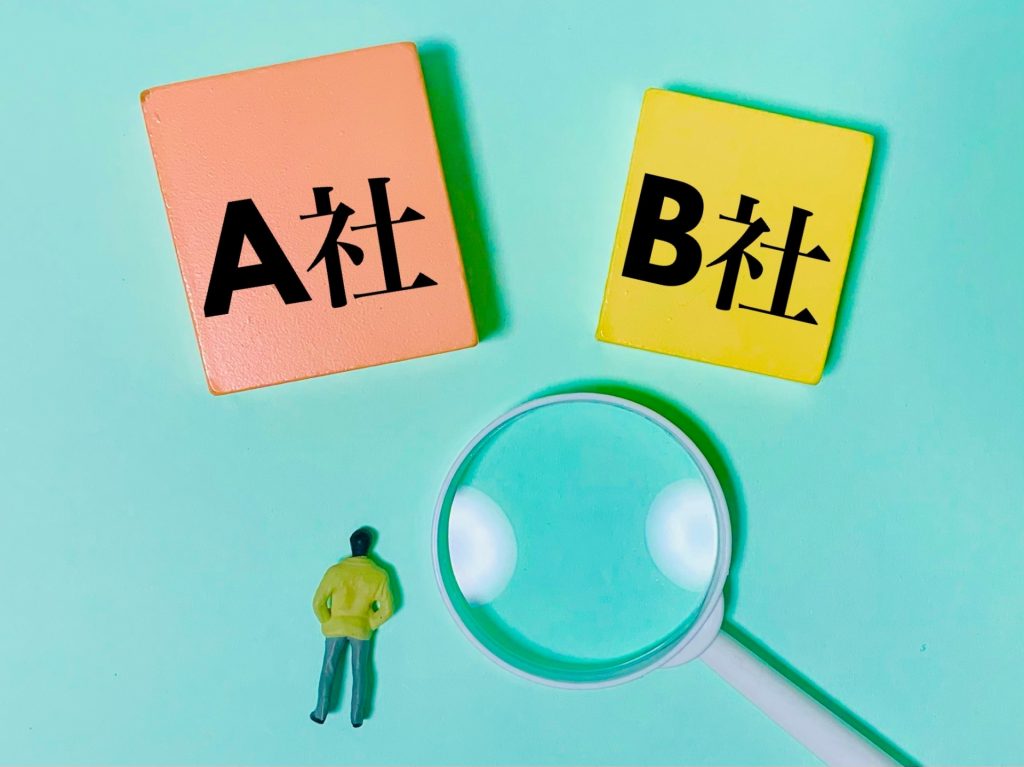
競合分析は、市場全体の状況やユーザーの価値判断の基準を「見える化」するための重要なステップです。数字をもとに他社と自社を比較することで、普段は気づきにくい弱点やチャンスを発見できます。また、主観ではなく客観的な視点から強み・弱みを把握できるため、優先すべき施策を論理的に判断できるようになります。
Webマーケティングは範囲が広く、限られた予算や人手をどこに使うかが成果を左右します。競合分析で得たデータをもとに、本当に改善が必要な部分にリソースを集中させることで、短期的な成果だけでなく、中長期的な成長にもつながります。さらに、明確な根拠に基づいた判断は、社内の合意形成もスムーズにしてくれます。
競合分析とは?
競合分析とは、自社と同じような商品やサービスを提供している他社のWeb戦略をデータで比較・分析することです。たとえば、以下のような情報を活用します。
- Webサイトのアクセス数
- 検索キーワードの人気度
- 外部サイトからのリンク状況(被リンク)
こうした情報を整理・比較することで、競合が何に力を入れているのか、自社と比べてどこに差があるのかを把握できます。ただマネするだけでなく、差別化のポイントや顧客のニーズに応えきれていない部分も見えてくるため、自社ならではの戦略づくりに役立ちます。
なぜWebマーケティングでは競合分析が必要なのか?
インターネット上のユーザー行動は日々変化しています。昨日うまくいった施策が、今日は通用しないということも珍しくありません。そのため、他社が新たに始めた広告手法やコンテンツの動きを定期的にチェックし、市場のスピード感に追いつくことが重要です。
競合分析を行えば、自社が出遅れている分野にいち早く気づけます。そこに優先的に予算や人材を投入することで、他社に先を越される前に対策が打てます。結果的に、競合にシェアを奪われるリスクを減らし、ブランドとしてのポジションも安定させやすくなります。
Webマーケティングで競合サイトを正しく見つける方法

競合分析を成功させるには、「誰と競っているのか」を明確にすることが出発点です。分析対象を間違えると、どんなに良いデータやツールを使っても正確な判断ができません。つまり、最初に「見るべき相手」を見極めることが、すべての戦略の土台になります。
検索結果やアクセスデータ、公開情報などを組み合わせて、業界の中で本当に影響力のある競合を見つけましょう。一度決めた選定ルールは記録しておくと、次回以降の分析もブレずに行えます。
検索キーワードから競合を探す
検索エンジンはユーザーが情報を探す入口です。そこで使われるキーワードを見ると、ユーザーが「どんな目的で検索しているか」が分かります。
まずは自社が狙いたいキーワードをGoogleなどに入力し、検索上位に表示されるサイトを一覧化しましょう。これらが「比較検討の場にいる競合」です。データはCSV形式で保存しておくと、順位の変動を追いやすくなります。また、同じ意味を持つ言葉(同義語)や関連語も調べると、より幅広く競合を見つけられます。
アクセスデータから競合を見つける
検索結果に出ない「隠れた競合」も存在します。これらはWebサイト分析ツールや広告プラットフォームのレポートから見つけることができます。
例えば以下のような点です。
- どのサイトから訪問が多いか(参照元)
- どの広告がよくクリックされているか
どのページが多く見られているか
などの情報を比較すれば、実際に影響力のあるプレーヤーを把握できます。分析する際は、季節変動の影響を避けるために、同じ期間でデータを比較しましょう。大規模データを使うときは、集計方法による誤差にも気をつけてください。
市場全体を見て間接競合も発見する
検索順位やアクセス数だけで見ていると、「別のカテゴリの競合」を見落とすことがあります。そこで、市場全体の地図(市場マップ)を描いてみましょう。たとえば求人サービスを提供している場合、競合は同じ求人サイトだけではありません。人材紹介会社、転職用SNSグループ、転職イベントなどもユーザーの選択肢です。
このように視点を広げて考えると、自社が想定していなかった競合や脅威も見えてきます。結果として、戦略の幅が広がり、より有利な立ち位置を見つけやすくなります。
Webマーケティングで競合分析するなら押さえておきたい4つの指標

競合分析では「何を見て判断するか」がとても重要です。見るべき指標が曖昧だと、せっかくのデータも意味を持たなくなってしまいます。ここでは、競合分析で必ずチェックしたい「4つの基本指標」をわかりやすく紹介します。
それぞれの指標を組み合わせて確認すれば、ユーザーが「サイトに来て」「関心を持ち」「離脱する」までの流れをつかむことができ、自社サイトのどこに改善の余地があるのかも見えてきます。
※同じ指標でもツールによって測定方法が違うため、1つのツールに統一して比較するのがポイントです。
①トラフィック量と流入チャネル
トラフィック量(アクセス数)は、競合サイトの「人気度」や「市場での存在感」を測る基本の指標です。
さらに、検索・SNS・広告・外部リンクなど流入チャネルごとに分けて見ることで、競合がどのチャネルに注力しているかがわかります。
たとえば、ある競合が最近SNSからのアクセスを急増させていれば、そこに力を入れていることが分かり、自社のリソース配分を見直すヒントになります。また、時間ごとのアクセス推移もチェックし、「季節的な要因」か「施策による成果」かを切り分けると、的確な対応ができるようになります。
②キーワードと検索意図の比較
競合と自社がどんなキーワードで重なっているのかを確認することで、本当の競争相手がどこかが見えてきます。また、そのキーワードが「情報収集目的」なのか「購入直前」なのかなど、ユーザーの検索意図もセットで見ることが大切です。
たとえば、購入を考えている人向けのキーワードで記事を書いているのに、内容が雑談的だったりすると、ユーザーは離脱してしまいます。こうしたズレは大きな改善チャンスです。
さらに、関連キーワードや類語も調べることで、漏れなく流入を拾える「ロングテール戦略」も強化できます。
③エンゲージメント指標(直帰率・滞在時間)
直帰率(1ページだけ見てすぐ離れた割合)と平均滞在時間は、サイトの「内容がちゃんと見られているか?」を表す指標です。この数値が他社よりも極端に悪いページがあれば、改善の優先度が高いと考えてよいでしょう。
最近は、動画やインタラクティブコンテンツを取り入れることで滞在時間を伸ばしているサイトも多くなっています。競合の成功事例を参考に、自社でも同じような仕組みを導入すると効果が期待できます。
また、直帰率が高いページは、「ページの読み込みが遅い」「ファーストビューで魅力が伝わらない」といった基本的な問題がある場合も多いので、デザイン面もあわせて見直しましょう。
Webマーケティングで競合分析を行う手順4STEP
競合分析はやり方が複雑になると、チーム内で再現できなかったり、時間がかかりすぎたりすることがあります。そこで本記事では、誰が担当しても同じ結果が出せるよう、競合分析の進め方を「4つのステップ」に分けてわかりやすく解説します。
各ステップをしっかり決めておけば、分析にかかる時間を短縮できるだけでなく、チーム全体の知見として蓄積しやすくなります。テンプレートを用意しておくと、作業の属人化も防げて便利です。
STEP1:競合を絞り込む
まずは「誰と競っているのか」を明確にすることが第一歩です。
- 自社の商品・サービスが属する市場をはっきりさせる
- 検索順位、アクセス数、広告出稿の有無などを参考に
上位5〜10社に絞り込むと分析の手間が減って効率的
競合を広く取りすぎると、分析が浅くなってしまいます。影響力の高い相手に集中しましょう。
STEP2:データを集めて見える形にする
次に、競合や自社のデータをツールから取得し、比較できるように整えます。
- アクセス解析ツールやSEOツールなどを使ってデータを収集
- 表やグラフにして「一目でわかる」形にする
- データを取った日時やツール名もセットで記録しておくと再分析しやすくなります
定期的にデータを取り、変化の傾向を見ることが大切です。
STEP3:フレームワークで整理する
データが集まったら、分析結果をわかりやすく整理します。便利なのが「フレームワーク」です。
- SWOT分析(強み・弱み・機会・脅威)やSTP(セグメンテーション・ターゲティング・ポジショニング)などを活用
- たとえば、自社のキーワード流入を「強み」に、競合に負けている部分を「弱み」に分類する
- 整理したマトリクスをチームで共有すれば、意見のズレも防げます
頭の中で考えるだけでなく、紙やスライドに「見える化」することがポイントです。
STEP4:戦略の仮説を立ててテストする
最後は、分析から得た気づきをもとに仮説を立てて実行に移します。
- 例:「このキーワードなら○○というペルソナに刺さりそう」
- 少額の広告出稿やLP改善など、小さく始めて効果を確認する
- 結果がよければ本格的に予算を投下してスケールさせる
この「仮説→テスト→検証」のサイクルを回すことで、競合に勝つための自社戦略がどんどん磨かれていきます。
Webマーケティングの競合分析に役立つツールの紹介
競合他社のWeb施策をしっかり分析するには、「どんなことをしているのか」「それがどれくらい成果を出しているのか」「自社と何が違うのか」を把握する必要があります。
そのために便利なのが、競合の広告・検索・出稿傾向などを把握できる専用ツールです。ここでは、特に役立つ3つのツールを紹介します。
①ドックピット
ドックピットは、国内サイトの検索流入や競合比較を一画面で把握できるクラウド型の可視化ツールです。直感的なUIで使いやすく、キーワードの検索ボリュームや推定クリック数、ランディングURL、順位の変動などを時系列で確認できます。
対象ドメインやURLを入力すると主要キーワードの検索ボリューム、推定クリック数、ランディングURL、順位変動、デバイス別シェアを自動集計し、競合サイトとのギャップや季節変動まで時系列グラフで可視化できます。
出力したレポートは営業資料にも活用でき、週次アラート機能で異常値の早期発見も可能です。こうした機能を活用すれば、競合の動きを定量的に把握し、優先的に取り組むキーワードやコンテンツの改善計画をより精度高く立てられます。
②FB広告ライブラリ
FB広告ライブラリはメタ社が運営する公開データベースで、世界中の広告クリエイティブと掲載開始日、配信停止履歴を誰でも閲覧できる透明性ツールです。
企業名やキーワードで検索すると画像、動画、コピー、表示地域、プラットフォーム別配信状況に加えてカルーセルやリールなどフォーマットごとのパフォーマンス傾向も一覧取得でき、ターゲティングの方向性と訴求パターンを定量把握できます。
保存機能やCSV出力も搭載されており、クリエイティブの変更履歴を時系列で追うことで、PDCAのサイクルやテスト戦略も読み取れます。複数ブランドの出稿順やテーマ展開を比較することで、自社への応用アイデアも見つけやすくなります。
③リスティング広告調査
検索連動型広告は入札キーワードや金額が非公開ですが、広告プレビュー機能やキーワード分析ツールを使えば、出稿傾向をある程度推測できます。
主要キーワードを定期的にチェックし、表示回数・広告文・リンク先などを記録していけば、訴求軸や配信量の変化が読み取れます。さらに、オークションインサイトを使えばインプレッションシェアも取得でき、季節による入札調整やテスト施策の有無も確認可能です。
こうしたデータを自社の広告施策と照らし合わせて分析すれば、差別化ポイントやLP(ランディングページ)の改善アイデアが明確になり、クリック単価が上昇しそうなタイミングも早めに察知できます。
その結果、キャンペーンの停止や再開の判断を、感覚ではなくデータに基づいてスピーディーに行えるようになります。
Webマーケティングで競合分析の結果を活かすコツ
競合分析は「数値を見て終わり」では意味がありません。重要なのは、その結果をもとにコンテンツや広告施策に落とし込み、実際の成果につなげることです。ここでは、競合分析の結果を自社のWebマーケティングに活かすための3つのポイントをわかりやすく解説します。
1. 差別化ポイントを見つけてコンテンツを改善する
競合と自社がどんなキーワードで勝負しているかを比べると、「他社と同じことを言っている領域」と「まだ誰も攻めていない領域」が見えてきます。たとえば、自社の強みがうまく反映されていないキーワードがあれば、そのキーワードで訴求の切り口を変え、コンテンツを書き直すと独自性が出せます。
また、ユーザーが求めているメリット(例:早く届く・安く買えるなど)を記事の中で一貫して伝えることで、信頼感を高めることもできます。施策を進める際は、改善内容をカレンダーで管理し、記事公開後の滞在時間や直帰率などを確認しながら、さらに修正を重ねていくとよいでしょう。
広告の入札戦略にも活かす
競合分析は広告運用にも活かせます。たとえば、コンバージョン率が高いのにライバルが少ないキーワードを見つけたら、そこに予算を多めに投下して、チャンスを逃さないようにしましょう。
逆に、競合が強い高額キーワードの場合は、時間帯や曜日ごとの成果をチェックし、効果が出にくい時間を外すとムダが減ります。
また、競合の広告文やバナーを参考にして、「自社の広告が似たような内容になっていないか?」を確認するのも重要です。違いが出せていないなら、数字などの根拠を示して説得力を強める工夫をしてみましょう。広告の入札戦略とクリエイティブはセットで見直し、週に一度くらいの頻度で結果を振り返ると改善サイクルが早く回ります。
競合分析を継続改善するポイント
競合分析は「一度やって終わり」ではありません。定期的にデータを更新し、振り返りを重ねていくことで、より実践的なヒントが得られます。ここでは、競合分析を継続的に改善し、効果を最大化するための2つのポイントを紹介します。
KPI設計とモニタリングフローを最適化する
KPI(重要な目標となる指標)は、会社全体の目標ときちんとつながるように設定し、担当者がすぐに行動に移せる具体的な数字にすることが大切です。たとえば、競合と比べて差が大きく出ている項目をKPIとして優先的に設定すれば、改善したときの効果もわかりやすくなります。
日々の運用では、「データを集める→見える化する→内容を振り返る→改善のアクションを決める」という流れを毎週のサイクルで繰り返すことで、分析のスピードを保てます。
また、あらかじめアラート機能を設定しておくと、データに異常があったときにすぐに担当者へ通知でき、早めに対応できます。KPIやアラートの基準となる数字は、3か月に一度見直して、会社の成長に合わせてアップデートすることが大切です。
外部パートナーを活用する
社内の人手や時間が足りない場合には、外部の専門会社やデータ提供サービスと協力することを検討しましょう。社外の視点を取り入れることで、自分たちでは見落としがちな競合分析のポイントに気づけるようになります。まずは短期間の契約で効果を見極め、その成果が確認できたら契約を拡大するという流れにすれば、無駄なコストを抑えつつ、リスクも減らせます。
また、外部ツールを導入するときは、自社のシステムと連携できるか(API対応など)や、集めたデータの所有権がどうなるのかをきちんと確認することが大切です。特定のツールに依存しすぎないように工夫すれば、長期的にも柔軟に運用できます。契約の更新時にはツールの効果を改めて見直し、自社で運用できる部分がないかも検討しましょう。
競合分析に基づく施策実行がWebマーケティング成功に大切
Webマーケティングの成功には、競合分析を活用した戦略と施策の実行が欠かせません。競合分析は単なるデータ収集ではなく、自社の強みや課題を見極め、マーケティング施策を進化させるための重要なプロセスです。客観的な指標から仮説を立て、すばやくテストと検証を重ねることで、変化の激しい市場でも柔軟かつ一貫した戦略を展開できます。競合を常に参照しながら分析と改善を続けることで、自社に最適なアプローチが見つかり、持続的な成果につながります。
Webマーケティングにお困りの方は、ぜひ一度お問い合わせください。